連載小説
連載小説「泡」 第二部「夢幻泡影」第4回 Posted on 2025/10/07 辻 仁成 作家 パリ
連載小説「泡」
第二部「夢幻泡影」第4回
上半身裸になった女性は、わずかに腰を屈め、落ちていた麻のシャツをサッと掴むと、それを翻すように宙で回し、袖に腕を通し羽織った。その時の腕と手のしなやかな動きは、女性特有のものだったが、男性に負けないほどの肩幅があり、胸の膨らみがなければ、痩せた男に見えなくもない。でも、やはり、内側から醸し出されるしなやかな存在感から、ミルコを想起させる。
「そこに座って」
その人物が指さしたのは、窓辺にある、たぶん、いつもアカリが座っている、モデルのための一人掛け用のソファだった。躊躇はあったが、話し合わないわけにもいかず、すすめられるがまま腰を下ろすことになる。その人は、画家の仕事椅子を持ちだし、俺の前に置き、そこに足を組んで腰を落ち着けた。
「さぁ、何から話しましょう」
女は、俺の目を覗き込み、顎を少し傾けながら言った。確信犯的な余裕というのか、口元がわずかに緩んでいるようにも、見えた。
「30分、待てるなら、メイクをして、あなたのよく知るあのミルコになれるけれど、どうする?」
「メイク?」
「ええ、カラコンを入れて、付睫毛をし、アイシャドー塗って、ウイッグかぶって、いろいろとやれば、いつものミルコが出来上がる。その方が、話しやすくない? 今は、きっと雰囲気や顔が違うからあなた戸惑っているでしょ?話したい相手があのミルコなら、ミルコになれますよ」
タキモトじゃなかった。そして、どうやらミルコでもなさそうだ。俺はもう一度、訊き返すことになる。
「でも、じゃあ、あなたは誰ですか? 俺はつまり誰と今、話をしてる?」
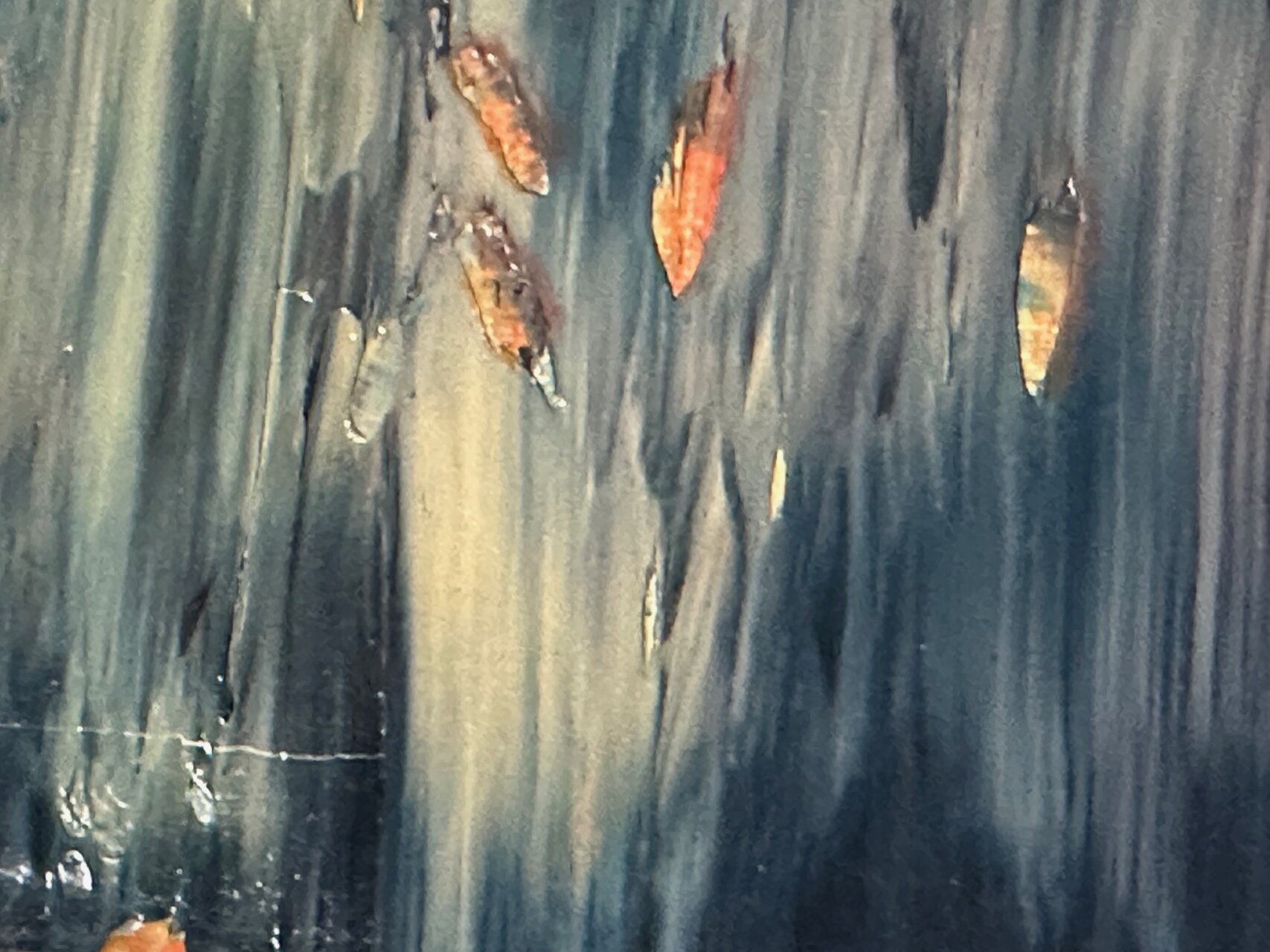
© hitonari tsuji
「わたしが誰か、それは重要ですか? わたしはミルコとタキモトの代理人でどうでしょう? さもなければ、その両方の分身。・・・これ以上、違う登場人物が出ても、混乱するだけだから、それに、わたしはミルコでもあり、タキモトでもあります、それは間違いありません。ま、戸籍上の本名はあるけれど、生物学的には、この通り女性だから、とりあえず、ミルコに近いかな。デパートの苦情係として10年働いていたのは事実、わたしなんだから・・・」
目の前に座す女の顔をしっかりと観察した。切れ長の上品な目を持ち、面長の輪郭、確かに女性にしては骨格もやや男性的かもしれない。顎もはっているし、やや尖っている。何よりも背が高いし、女性にしては声も太く掠れている。つまり中性的で、髪が短ければ、男性と言われてもおかしくはなかった。ただ、細い鼻筋がしゅんと通っており、そこが、この人を女性的に見せる唯一のフェミニンな要素かもしれない。
「あなたが誰だか分からないけれど、それがオリジナルのミルコであり、オリジナルのタキモトであるならば、別に名無しのままでも構わない。幻じゃなく、実在する人間であるならば、その方がいい。今は真実を知りたいだけなんで、・・・。ただ、なんで、男であるタキモトになったり、妖艶なミルコに化けたりしないとならなかったの?」
いろいろ質問したいことがあったが、とりあえず、今もっとも、混乱の根本にある謎について、問いただしてみた。不意に出現した中性的な女は、小さく頷くと、そうね、そうよね、と同意した。女は一度、窓外へと視線を向け、人生を振り返るように、言葉を選びながら、語り始める。
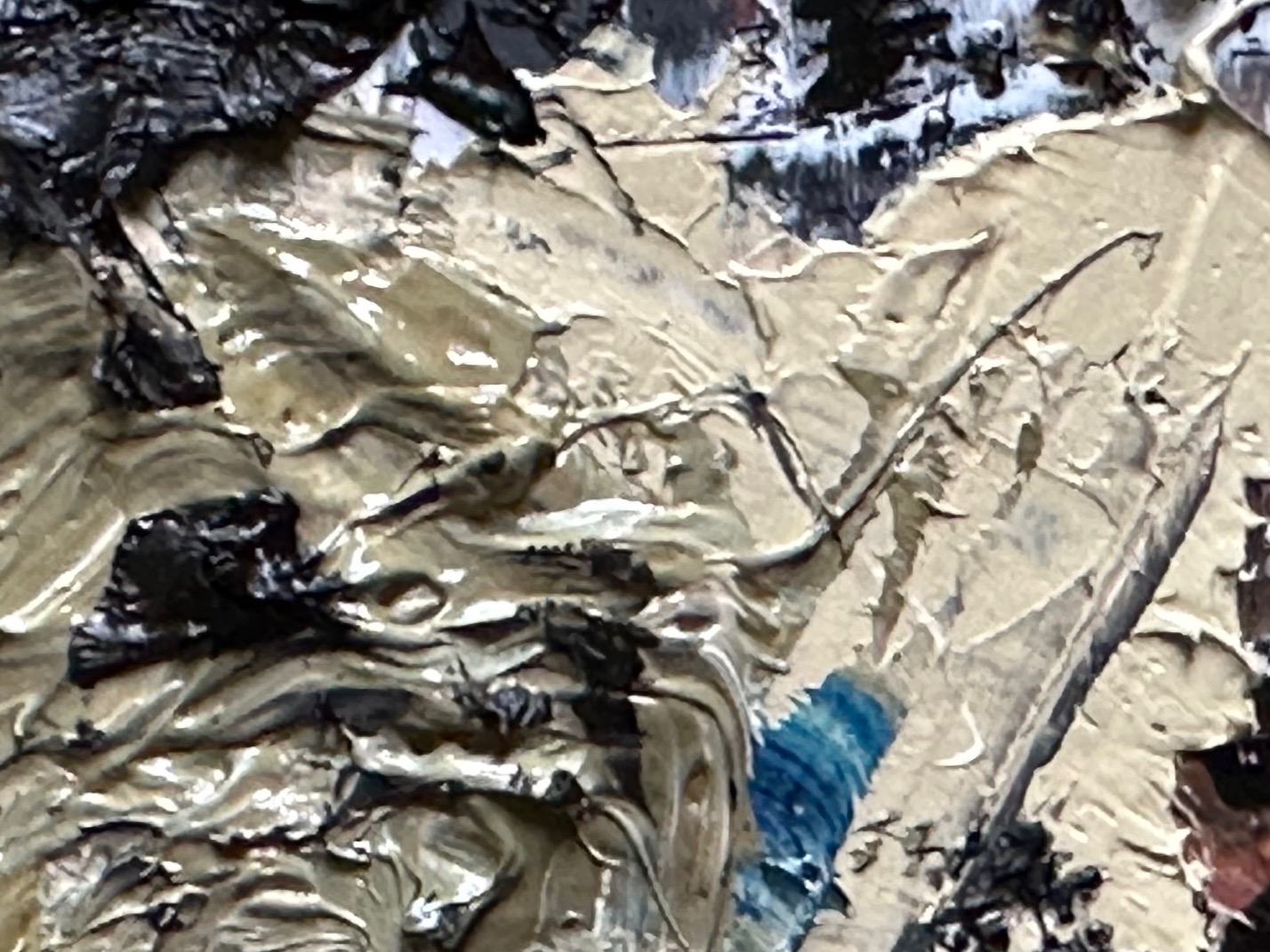
© hitonari tsuji
「ある時、自分はすでに死んでいるんじゃないかって、考えるようになった。東口駅前のデパートで長いこと苦情係をやっていたんだけど、辛かった。人からの苦情や訴えを聞き過ぎて、心がすり減っちゃって・・・。びっくりするくらい世の中の苦情というものは容赦がないし、リスペクトすらないのよ。だから、人生の掃きだめみたいなところで溺れかかった。いつも行き交う無数の人をかき分けて出社し、数限りないクレームを処理しているうち、そうね、知らない人に怒られるたびに心を殺さないとならなかったから、次第に自分が消えかかり、自分を失くしそうになった。わたしは何も悪いことしてないのに、謝るのが仕事だったのよ。そして、わたしは入社からずっとその仕事だけを任され続けてきた。ある意味、上手だったの、心を殺して謝るのが・・・。同期入社の中では大いに出世はしたけれど、でも、本当は販売員になりたかった。ま、それも運命よね。ずっと、苦情の処理・・・。まさに、死んでいるように生きてきた。ある時、自分はとっくに死んじゃったんじゃないかって、考えるようになる。生き地獄みたいなところを彷徨ってる、まるで浮遊霊のような感じ?」
女は、思い出すように、微笑んで見せた。笑いだしそうになるのを、堪えているようにも見えた。
「それにしても、たいしたクレームじゃないのよ、中にはちゃんとした苦情もあったけれど、ほとんどは、人々の腹いせのような、下らない文句。10年も、そういう人たちの気持ちをぶつけられてごらんなさい。大事な仕事だってことは理解出来ていたし、責任感もあったけど、まともでいられるわけがない。死んでいるように生きるようになっても不思議じゃないでしょ。だんだん、この世界は幻じゃないかって、思うようになっていく・・・。ある意味、苦しみからの逃避ね」

© hitonari tsuji
女は笑った。でも、すぐに真面目な顔に戻って、続けた。
「君は自分が、実は死んでいるのにそのことに気が付かなくて、現世界を彷徨っているんじゃないかって考えたことない?ないか。でも、わたしはあるの。生と死の境目は非常に曖昧だからね。しゅう君、考えてみて、あなたは自分が死んでない、という自信ある? 突然死したら、肉体は死んでも魂は死を理解出来ずに彷徨ったりするって言うじゃない? そもそも、何が生きているという根拠になるわけ? わたしと話しているから? アカリさんの問題で苦悩しているから? 誰かを殴りつけたから? お腹がすくから? でも、それが幻想だと思ったことはないの? すでに死んでいるのに、それに気が付かないで、まるで夢を見ているようにこの現世と重なって生きたふりして彷徨っているだけってことはない? あり得るでしょ?」
女が矢継ぎ早にそのようなことをぶつけてきた。気持ちは分からないでもなかったが、正直、俺の知識や経験だけでは理解することが出来なかった。生きてないなら、こんなことで悩むこともない。でも、地下道の仙人は『自分が生まれた瞬間の記憶がないように、人間は死ぬ瞬間が分からないのだから、実は、永遠に生き続けることになる。これが真実だ』と言った。その時も意味が分からなかったが、始まりも終わりも今を生きる人間にはわからない、ということは事実で、じゃあ、生死って、なんだ? つまり、生きているのか死んでいるのか、をはっきり証明できる人間はだれ一人いないということじゃないのか。この女が、そこで苦しむのは真っ当なことかもしれない。なぜなら、俺にだって、いやあらゆる人間に、生まれた時の記憶はないし、きっと死ぬ瞬間の記憶なんか幻でしかないはずだから・・・。つまり、生まれたのも疑わしく、死ぬのは誰にも分からない、ということ。この目の前の女性の不安は、そういう生と死の曖昧さ故からのものだろう。真面目過ぎるのか、頭が良すぎるからこんなことで悩んでしまっているのか・・・。人間は能天気に生きることも必要なのだ、と俺はその時、心の底根で気が付いた。
「でね、そういう苦悩の日々にいたんだけれど、数年前、ある日、ミルコがどこからともなく、わたしのところにやって来たのよ。鏡の中に映っている自分が、わたしに、もう一人の自分がいるわよ、と言い出した。鏡を覗くと、確かに、何かがいた。自分なのだけれど、自分じゃない、もう一人の自分・・・。それで、導かれるように、メイクをしてみたの。なんか、そうしないといけないような気持ちになって、普段、まともな化粧なんかしないくせに、いい口紅を引っ張り出し、それを塗り、アイライナーを引いてみた。そしたらね、そこにわたしじゃないもう一人のわたしが立った。それがミルコだった。苦情係の自分とは違うもう一人の、奔放で自由な女、ミルコとの出会い・・・」
女の目は、暗く沈んでいた闇を払拭し、生き生きと輝きだしていた。
「ミルコが、わたしに向かってほほ笑んだのよ」
次号につづく。
※本作品の無断使用・転載は法律で固く禁じられています。

© hitonari tsuji
辻仁成、個展情報。
☆
パリ、10月13日から26日まで、パリ、ピカソ美術館そば、GALERIE20THORIGNYにて「辻仁成展」2週間、開催。
☆
1月中旬から3月中旬まで、パリの日動画廊において、グループ展に参加し、6点ほどを出展させてもらいます。
posted by 辻 仁成
辻 仁成
▷記事一覧Hitonari Tsuji
作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。




