連載小説
連載小説「泡」第三部「鏡花水月」第6回 Posted on 2025/11/08 辻 仁成 作家 パリ
連載小説「泡」
第三部「鏡花水月」第6回
「来ちゃった」とアカリが言った。
「アカリ・・・。マジで、アカリ?」
「そうよ、当たり前でしょ、忘れちゃたの?」
俺は嬉しくなって、口許が、震えながらもほころぶのだった。いや、これは夢かもしれない、さっき、俺は昼寝をしてたんじゃなかったっけ・・・。
「ほんとに、アカリかよ。でも、どうやって、ここが・・・。あ、」
「そう、エアタグが案内してくれた。ずっとあの事件のあと、心配して、『探す』ってアプリ、毎日、欠かさず見続けてた。一日2,3度は、覗き込んで確認してたんだよ。だけどさ、青い丸、ずっと灯らなかった。ちょっと諦めかけていた。それでも、いつか、きっと見つかるって、信じてもいた。そしたらね、不意に青丸が灯ったから、びっくりしちゃって・・・」
「そうか・・・」
泣きそうになったが、口で呼吸をして、泣くのを必死で堪えた。アカリが笑っているのに、俺が泣くわけにもいかない。
「で、確かめないと、ほんとうにしゅうがいるか分からないじゃん、ラインとかする前に、身体が先走って、で、来ちゃった」
「・・・嬉しい」
「あの」
振り返ると、母親がにやにやしながら、戸口に立っていた。
「そんなところで話さないで、よければ、どうぞ。わたしは邪魔しませんから、しゅうの部屋で、二人で、水入らず、話したらいいんじゃないかしら。コーヒーはないけれど、お茶ならありますよ」
「お母さま、ありがとうございます。じゃあ、お邪魔させて頂きます」
そう言うなり、アカリはそのまま、まるで自分の家に戻るような感じで、勝手に家の中へと入っていった。俺は慌てて、後を追いかける。

© hitonari tsuji
俺の家にはソファなんて気の利いたものはないから、俺たちは俺の部屋の狭いベッドに並んで座って、窓の向こうの芦原を見ながら、お茶に口をつけた。ちょっと風通しを良くするために、外に繋がる大きな窓を全開にした。そこには昔、父親が日曜大工で作った畳一畳ほどのデッキがあって、昔はそこから飛び出し、海水パンツを履いたまま、海の中へと飛び込んでいた。
「すごい、なんか、ここ、めっちゃ最高な場所だね」
「だろ。外観はボロだけれど、でも、海の家って感じすんだろ」
「こういうところでしゅうちゃん、育ったんだね。羨ましい。あんな素敵なお母さんがいて・・・」
そうか、そうだった。この子は施設で育ったんだっけ、と俺は思い出していた。親を知らない、正月が誕生日だけれど、それは誰かが勝手に決めた誕生日だったんだっけ・・・。アカリの生い立ちを思い出し、不意に俺の口許が固まってしまう。
アカリは立ち上がり、湯飲みをお盆の上に置いてから、窓の方へと行き、葦原の先の浜辺、その向こうの輝く海を見つめた。俺もそっと立ち上がり、幻想のような現実を確かめるために、彼女の後ろに寄り添うように立った。
「しゅうちゃん、子供の頃、あの海で毎日、泳いでたんでしょ?」
「そうだな。あそこは俺の海だから」
「かっこいい、俺の海とか、言ってみたい」
俺たちは微笑みあった。一瞬、あの街での二人の暮らし、二人が関係した世界のことが頭を過った。コカ・コーラの赤いネオン看板、くねるように続く路地、酔っ払い、観光客、黒服、ホスト、地回り、ごった返す様々な人々、朝まで眠らない不夜城、行列の途切れないラーメン屋、高層マンションから見えたコンクリートの地平線、地下世界・・・。
「別世界ね、ここ」
「そうだな。ぜんぜん違う」
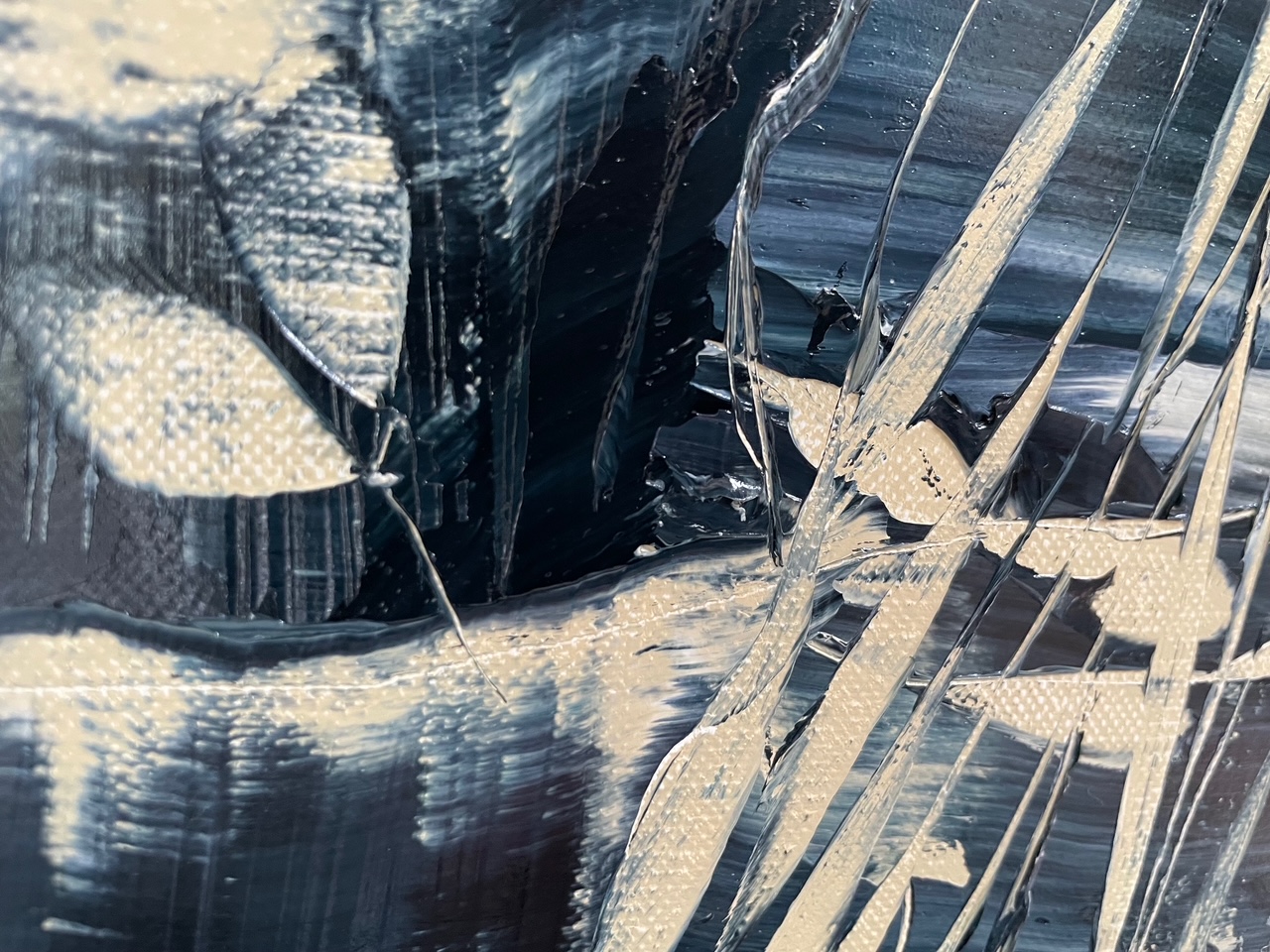
© hitonari tsuji
あの事件のあと、あの街がどうなったのか、一瞬、アカリに聞こうか迷ったが、今のこの穏やかな空気を壊したくなかったので、俺は野暮な質問は控えることにした。でも、これから、どうするのだろう、と思った。アカリとの会話は弾んだが、アカリが傍にいることを、俺はいつまでも、実感することが出来ずにいる。これも泡のようなものかもしれない、と疑ったからだ。もうすぐ、きっとこの幸福も弾け飛んでしまう。警戒しないといけない。これは幻に過ぎないのだ。俺は、幸福の絶頂から叩き落とされる前に、嘆息を溢し、身構えるのだった。
「でも、信じられないんだよ。ここに今、この瞬間、目の前に、アカリ、お前がここにいるってことが・・・」
「よね、わたしも・・・。ここまで来るの、めっちゃ時間かかったし。AIに教えて貰って、電車とバスを乗り継いでやっと来ることが出来たし。何時間もかかったし、バス降りてからさらに遠いじゃん、途中で、マジで、辿りつけるか、心細かった。でも、会えて安心してるよ」
「ありがと、で、今日は、どうすんの? この時間から戻るつもり?」
「泊ってっていい?」
「あ、いや」
俺の家はあまりに狭すぎて、アカリが泊まれる余分な部屋がない。キッチンの向こう側に両親の部屋はあるが、それだけ・・・。俺の狭いベッドにアカリを寝かせて、俺がキッチンにゴザでも敷いて寝るか、・・・。
「このベッドでさ、二人で昔みたいに寝ようよ。別に、寝ないで、朝まで話していてもいいよ」
ノックの音がした。母親が顔を出した。
「あの、夕飯どうする? お嬢さん食べていくかしら」
「はい、頂きます」
アカリが元気いっぱい、返事をした。すると、母親は笑顔になり、
「じゃあ、泊まっていく?」
と言い出した。
「はい、泊まります」
「了解。じゃあ、ご飯作るわ。なんにもないけれど、父さんに魚を買ってきてもらう」
「わ、嬉しい」

© hitonari tsuji
夜、奇妙なことが起きた。俺の両親とアカリと俺が同じテーブルを囲んで、夕食を共にしたのだ。自慢の母親の料理だったが、気の利いたものは一つもなく、アカリが喜ぶのか、気になった。けれども、アカリは「美味しい美味しい」と言いながら、煮っころがしや、焼き魚や、お茶碗いっぱいのご飯なんかを食べ切ってしまった。
「この家にお客さんが来るの、何年ぶりかしら。しかも、しゅうの恋人さんだなんて、すごくない? あなた。これ、奇跡かもよ」
話をふられた父親は黙っていたが、あの父にしては珍しく、ポカンとした顔で、アカリを見ていた。
「あなた、じろじろ見ちゃだめよ」
「あ、バカ息子が、その、そのですね、世話になっております」
と父が珍しく頭を下げた。俺は焦った。みそ汁を飲みかけていたが、噴き出しそうになった。すると、アカリが、
「はい、末永くよろしくお願いいたします」
と言った。
次号につづく。
※本作品の無断使用・転載は法律で固く禁じられています。

© hitonari tsuji
posted by 辻 仁成
辻 仁成
▷記事一覧Hitonari Tsuji
作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。



